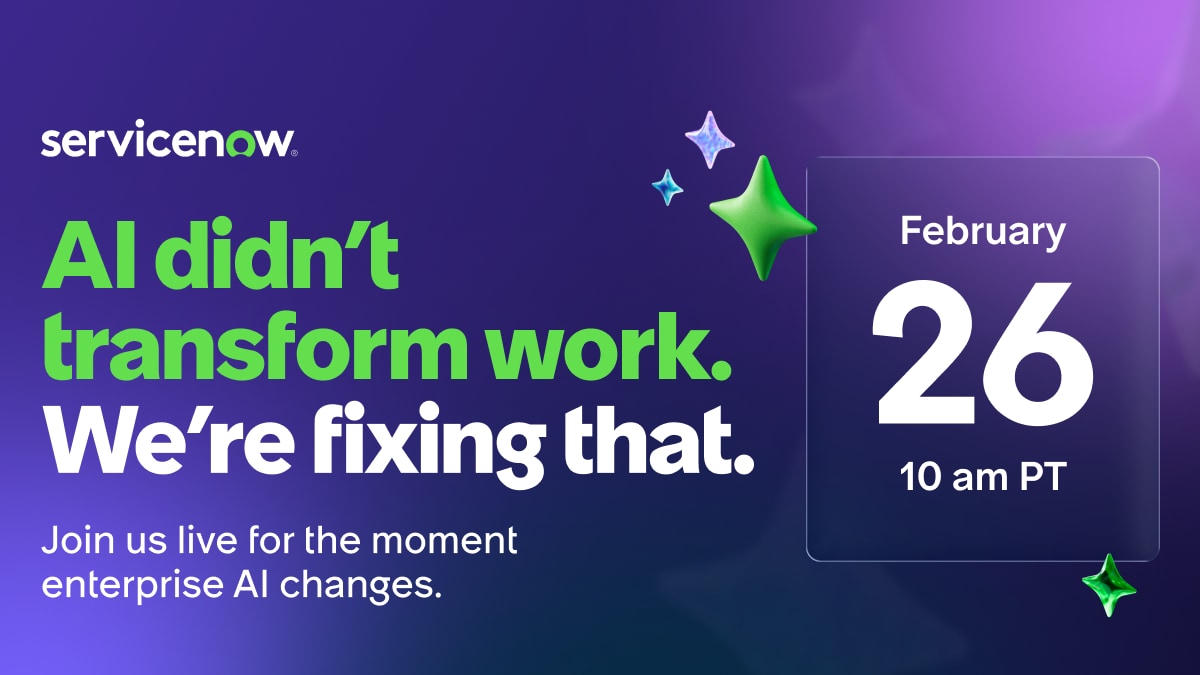- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
こんにちは
新しく始まったブログシリーズの本編第1回です。
各回へのリンクが含まれる導入編についてはこちらの記事をご確認ください。
野中・竹内両氏の組織的知識創造理論は、現代のナレッジマネジメントの根幹を成す重要な理論体系です。その中核にあるのが「SECIモデル」であり、知識とは静的な情報ではなく、暗黙知(言葉にできない知恵や経験)と形式知(言語化された知識)が相互作用しながら動的に創造されていくプロセスであると定義しています。
このモデルは以下の4つの知識変換モードで構成されています:
- 共同化(Socialization) – 暗黙知から暗黙知への変換。例えば職人が見習いに技術を「見せて覚えさせる」ような、身体的な経験や空気感を通じた伝達。
- 表出化(Externalization) – 暗黙知から形式知への変換。比喩・類推・モデルなどを通じて、暗黙的な洞察を言語や図表に落とし込む作業。
- 連結化(Combination) – 形式知から形式知への変換。複数の形式知を収集・分類・統合し、新たな体系を構築する。
- 内面化(Internalization) – 形式知から暗黙知への変換。マニュアルや資料を通じて得た知識を実践の中で体得し、自らの知恵として再吸収する。
この4つのモードは直線的ではなく循環的に連鎖し、知識が組織内でスパイラル状に増幅していきます。SECIモデルは単なる知識の整理法ではなく、組織がイノベーションを生み出すための「知のダイナミズム」を可視化したものなのです。
SECIモデルの理解は、以下のような問いに対する答えを与えてくれます:
- 組織はどのようにして属人的な知恵を共有可能な知識に変えるのか?
→組織は「共同化(Socialization)」と「表出化(Externalization)」のプロセスを通じて、個人の暗黙知(属人的な知恵)を形式知(共有可能な知識)へと転換する。まず、共同化で経験や感覚を共有し、暗黙知同士を交換することで知識の基盤をつくる。次に表出化によって言語化や図式化などを通じて暗黙知を形式知に変換し、他者が理解・共有できる形にする。これにより、属人的な知恵が組織全体で活用可能な資産となる。
- 形式知はどうすれば新たな意味づけを持って進化するのか?
→形式知は「連結化(Combination)」と「内面化(Internalization)」のプロセスによって進化する。連結化で既存の形式知同士を組み合わせたり編集・再構成したりして、新しい形式知を創り出す。次に内面化で、個人が新たな形式知を実践や経験を通じて自分の暗黙知として取り込み、理解を深める。こうして形式知は単なるデータや情報の集積から、意味づけを伴う生きた知識へと進化する。
- 組織の学習とは単なる記録の蓄積ではなく、どのように“生きた知識”となるのか?
→組織の学習は、SECIモデルの4つの知識変換プロセスを繰り返す「知識スパイラル」の中で継続的に進行する。単なる情報や記録の蓄積ではなく、個人やグループ間の暗黙知と形式知が動的に交換・変換されることで、知識が深化し新しい価値が創出される。このプロセスが組織の文化や場(Ba)に根づくことで、「生きた知識」として組織全体に浸透し、イノベーションや持続的な学習を支える。知識スパイラルや場については第2回、第3回で詳しく触れます。
このように、SECIモデルを深く理解することで、単なる情報管理を超えた「価値ある知識創造」の視点が得られるのです。
次回投稿(第2回)では知識スパイラルについて解説します。
- 890件の閲覧回数