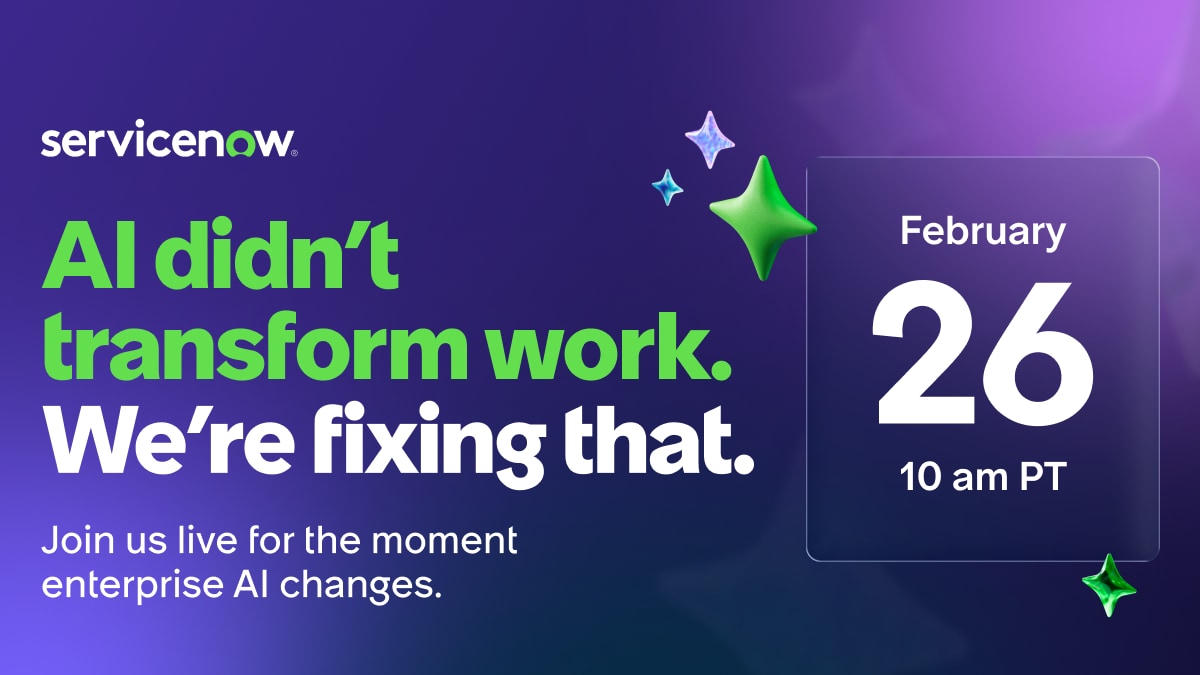- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
こんにちは。
今回の投稿はこれから始まる全6回のブログシリーズの導入編です。
先日(2025/7/31)に開催されたAI Learning Daysでも私が取り上げた知識創造理論についてもう少し詳しく説明します。
同様の内容を英語でも投稿しています。英語でのシリーズはこちらの導入編をご確認ください。
1990年代に野中郁次郎氏と竹内弘高氏によって提唱された「知識創造理論(The Knowledge-Creating Theory)」は、日本企業のイノベーション力を世界に紹介する画期的な理論として注目を集めました。彼らの代表的な論文「The Knowledge-Creating Company」は1991年に『Harvard Business Review』に掲載され、その後、1995年には英語書籍 The Knowledge-Creating Company として出版、さらに1996年にはその日本語訳『知識創造企業』が東洋経済新報社より刊行されました。
出典:東洋経済新報社『知識創造企業』書籍紹介ページ(https://str.toyokeizai.net/books/9784492522325/)
この理論では、企業が暗黙知と形式知を循環させながら新たな知識を創造するプロセスが体系化されており、SECIモデル(共同化・表出化・連結化・内面化)を中心に構成されています。
もちろん、この理論が提唱されたのは30年以上前であり、特に近年では生成AIの急速な進展によって、知識の収集や整理といったプロセスの多くがAIによって代替されつつあります。しかしながら、ゼロから新しい意味や価値を見出す「知識創造」の本質的な部分については、いまだに人間の関与が不可欠であることに変わりはありません。
このブログシリーズでは、1991年の論文「The Knowledge-Creating Company」(Harvard Business Review掲載)および2000年の論文「SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation」(Long Range Planning掲載)を参照しながら、この理論の枠組みを現代の文脈でわかりやすく解説していきます。
シリーズを読み進めていただくと、これらは新しい理論ではなくこれまで我々が日常的に実践してきたことが整理されているのだと気づくと思います。
そうすることでその日常的な実践の場の中で何か欠けているプロセス、場、資源などはないか?と確認できるのです。
小さな発見のために是非このシリーズをご活用ください。
本シリーズは以下の6回で構成されています:
- SECIモデル:知識変換の4つのプロセス
- 知識スパイラル:組織を超えて広がるイノベーション
- 場(Ba):知識が生まれる「文脈としての場」
- 知識資産:知識創造を支える4つの資源
- 知識創造を支えるリーダーシップと支援条件
- ServiceNow UniversityとSECIモデル:知識創造理論を学習プラットフォームに活かす
次に6回の各トピックの概要を説明します。
- SECIモデル:知識変換の4つのプロセス
SECIモデルは、暗黙知と形式知の間の知識変換プロセスを「共同化・表出化・連結化・内面化」の4つのモードで説明します。今日の職場では、生成AIを活用することで、例えば口頭で話された暗黙知をテキスト化(表出化)し、ドキュメントにまとめる(連結化)といったプロセスがよりシームレスに行われるようになっています。SECIモデルは依然として、組織内外での知識共有や学習を理解するための強力なフレームワークです。
- 知識スパイラル:組織を超えて広がるイノベーション
SECIプロセスは一度きりではなく、個人からグループ、組織、さらには業界全体へと広がる「知識スパイラル」を形成します。リモートワークやオンラインコミュニティが一般化した今、知識スパイラルは物理的な組織を超えて加速しています。生成AIは、業界をまたぐナレッジ共有やベストプラクティスの抽出にも活用され、スパイラルの成長をさらに後押しします。
- 場(Ba):知識が生まれる「文脈としての場」
「場(Ba)」は知識創造のための文脈や空間を意味します。物理的な会議室から、バーチャルなコラボレーションスペース、AIによる対話型学習環境まで、多様なBaが存在します。現代のBaは、デジタル技術とAIによって時間・空間を超えて形成され、知識の共創を加速させています。
- 知識資産:知識創造を支える4つの資源
知識創造には、経験的、概念的、体系的、実践的という4種類の「知識資産」が関与します。生成AIは、概念の可視化(概念的資産)や、ナレッジベースの整理(体系的資産)に特に貢献しています。これらの資産をうまく管理・活用することで、継続的な知識創造と組織学習が可能になります。
- 知識創造を支えるリーダーシップと支援条件
知識創造には、目的志向のリーダーシップ、組織文化、インフラストラクチャー、インセンティブなどの支援条件が不可欠です。AI導入を成功させるには、単に技術を使うだけでなく、それを活用する文化やリーダーの推進が必要です。知識創造を阻害しない環境づくりが、現代のマネジメントには求められています。
- ServiceNow UniversityとSECIモデル:知識創造理論を学習プラットフォームに活かす
ServiceNow Universityを通じた学習では、SECIモデルの各要素を体験できます。ユーザー同士の協働(共同化)、学習コンテンツの視覚化(表出化)、統合された知識ポータル(連結化)、そして業務適用(内面化)を通じて、実践的な知識創造が促進されます。生成AIによる個別化学習やナレッジ生成機能も今後さらに強化される見込みです。
それではそれぞれの各回の投稿をお楽しみに!
- 1,990件の閲覧回数